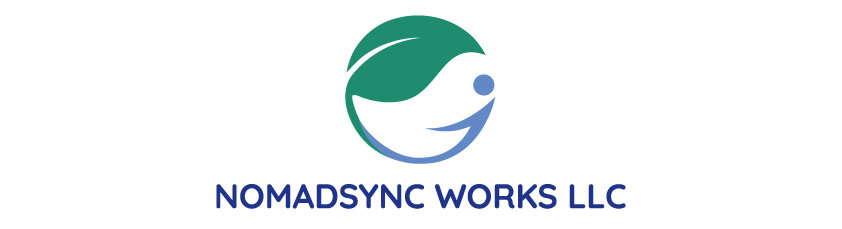はじめに
ここ数年で生成AI、特にGPTを業務に取り入れる事務所が増えました。
私自身も、月次報告書や経理データの整理を効率化するために「マイGPT」を作り込み、日々の現場で試しています。
しかし実際に運用してみると、単なる「便利ツール」とは言い切れない難しさが見えてきます。
特に、GPTは同じデータを与えても出力が毎回同じとは限らないという点です。
会計現場で実際にあった「ブレ」の事例
同じCSVを読み込んだのに違う答え
月次の試算表データをCSVで読み込ませ、「人件費率を算出してください」と指示しました。
ある時は、試算表の「給料手当」「業務委託料」「法定福利費」を正しく拾って計算してくれたのに、別の時には「交際費」まで人件費に含めてしまう。
同じマイGPT、同じCSVなのに結果が異なるのです。
雛形を無視して余計な提案をする
「このフォーマット以外では出力しないでください」とプロンプトで強く指定しているのに、急に「財務分析を追加しました」と余計な章立てを勝手に入れてくる。
使っているこちらとしては「いや、頼んでない!」という気持ちになります。
営業日数の計算がブレる
Squareの売上データを読み込ませ、営業日数を算出させたときのこと。
午前0時台の決済を「前日の売上」と解釈するか「当日の売上」と解釈するかで答えが変わり、営業日数が16日になったり17日になったり。
人間なら状況を確認して判断できますが、GPTはその線引きが曖昧なまま出力してしまいます。
なぜこうしたブレが起きるのか?
GPTがブレる理由は大きく3つあります。
- 指示が曖昧
「人件費率を出してください」とだけ指示すると、人件費の範囲を勝手に解釈してしまう。 - 確率的な仕組み
GPTは「次に続く可能性の高い単語」を選んで文章を組み立てています。確率の揺らぎによって、同じ入力でも違う出力になるのです。 - 知識と指示の優先度
マイGPTに知識を登録していても、指示が強すぎると知識を無視したり、逆に知識を過剰に優先して指示を外れることがあります。
会計現場での工夫
- 勘定科目を明示する
「給料手当・業務委託料(ホステス報酬)・法定福利費のみを人件費とする」と具体的に列挙して指示する。 - 参照ルールを文章化する
「営業日は売上があった日を1日とカウントし、午前0時台の取引は前日の売上とする」など、データ解釈ルールをプロンプトに含める。 - 人間が必ず検算する
GPTに任せきりにせず、最後は試算表や総勘定元帳を見て「人件費率が合っているか」「営業日数が正しいか」を検算する。 - 複数回試す前提で使う
「一度で完璧」は期待せず、数回やり取りして最適解を引き出すスタンスを持つ。
まとめ
GPTは会計現場において強力な効率化ツールですが、万能ではありません。
むしろ「人間のように解釈が揺らぐ」からこそ、思わぬブレが生じます。
大切なのは、どこまでAIに任せ、どこから人が調整するかの線引きを明確にすること。
会計のように正確性が求められる分野では、GPTに集計やフォーマット化を任せつつ、最終的な判断は人が行うのが現実的です。
万能ではないからこそ、得意な部分だけを切り出して使う。
それが、生成AIと会計現場がうまく共存するための一歩だと感じています。